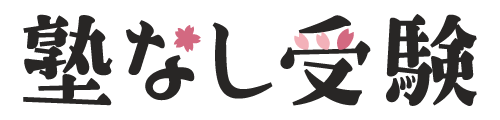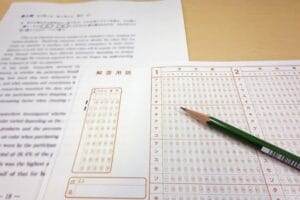この記事は「長女の公立高校選び」シリーズの第5回です。
最終回となる今回は、実際に高校選びを経験して「やってよかったな」と感じたこと、逆に「もっと早く知っていれば…!」と反省している点をまとめていきます。
これから高校選びをする中学生や保護者の方の参考になればうれしいです。
前の記事はこちら↓
志望校決定のきっかけと親子の葛藤|長女の公立高校選び04
夏の全県模試の結果を受けて、偏差値がまったく足りていない状態でも「それでもS高校に行きたい」と決めた長女。 でも、思いとは裏腹に、勉強量は一向に増えませんでした。 「これやって」「あれやって」と指示をしても、結局やらない […]
「長女の公立高校選び」シリーズ一覧
やってよかったこと
早いうちに優先順位を決めたこと
長女の受験に本格的に動き出したのは中学2年の夏頃でしたが、実は「高校を選ぶときに何を大事にするか」という話は、中1のうちにしていました。
長女の場合、「高校でも部活を続けたい」という思いが強く、自然と「部活が続けられる高校」という視点で絞り込めたのはとてもよかったです。
高校を選ぶ基準っていろいろありますよね。
- 学科(普通科・工業科など)
- 部活動
- 偏差値
- 進学率・進学先(指定校推薦など)
- 家からの距離
- 駅からの距離
- 友人や在校する兄弟の有無
全部を満たす高校なんてなかなかないので、「何を一番大事にするか」を親子で共有しておくことはとても大切だと感じました。
特に塾なしで受験する場合、
- 周りの状況が見えにくい
- 受験モードに切り替わりづらい
- 進路についての助言が受けにくい
など、どうしても“情報不足”が起こりがちなので、早いうちからぼんやりでも方向性を話しておくと、後々とてもスムーズです。
中1の頃の会話は、
私「高校でも部活、続けたいの?」
長女「うーん、続けたいかな〜?」
くらいのゆるいものでしたが、それが「じゃあ部活で選んでみようか」という第一歩になりました。
文化祭に行ったこと
志望校候補の文化祭に行ったことで、「この学校に行きたい!」という気持ちが一気に強まりました。
パンフレットやHPでは分からない、学校の雰囲気が肌で感じられたようです。
文化祭は、受験学年でなくても行けるので、中1・中2のうちに複数校見ておくのが◎。
3年になると部活の大会や定期テスト、模試、学校説明会などでスケジュールが詰まりがちなので、早めの行動が本当に大事でした。
全県模試を活用したこと
長女のように塾に通っていない子にとって、全県模試はとても頼りになる存在でした。
過去データの蓄積も豊富で、受験者数も多いので、自分の位置が客観的に把握しやすいです。
第1志望に関する情報だけでなく、成績が伸びなかったときの第2志望を決めるときにもすごく参考になりました。
反省点・もっとこうすればよかったこと
志望校の視野が狭すぎた
最初は「部活があって家からも近いM高校しかない!」と思い込んでしまい、他の学校を調べるのが遅れてしまいました。
結果として志望校を変更することになり、さらにランクを下げた時の高校も新たに候補が出てきたのですが、説明会や文化祭に参加できず、情報がほとんど得られないまま選ぶことに…。
「この高校に行きたい」ではなく、「こういう高校に行きたい」「もしランクを変えるならどう動くか」など、広めの視点で見ておけばよかったなと思います。
情報収集が後手に回った
内申と当日点の比率など、調べておくべきことがたくさんあったのに、最初の頃はその重要性に気づいていませんでした。
3年の秋ごろになってようやく焦って調べ始めることに…。
もっと早く、受験全体の流れや制度を親が把握していれば、長女にも落ち着いて情報を共有できたはずです。
最後に
高校選びは、「通える高校」ではなく「通いたい高校」を見つけることが何より大切だと実感しました。
一方で、1校に絞りすぎず、複数の候補や「譲れる条件・譲れない条件」を話し合っておくことも、同じくらい大事です。
正解のない選択だからこそ、「自分たちなりの納得感」を持てるように動くことが、受験期を前向きに過ごすカギになると思いました。
これで、長女の高校選びに関する記録はひと区切りです。
ここまで読んでくださった方、本当にありがとうございました!
番外編はこちら↓
後悔しない併願校の選び方!準備が遅れて焦った我が家の体験談|長女の公立高校選び【番外編】
高校受験で悩むポイントのひとつが、「私立の併願校をどうするか?」という問題。 我が家も最初は「併願はしない!」と決めていました。でも最終的には、併願校を受験することに。 今回は、私たちが実際に体験した、私立併願にまつわる […]